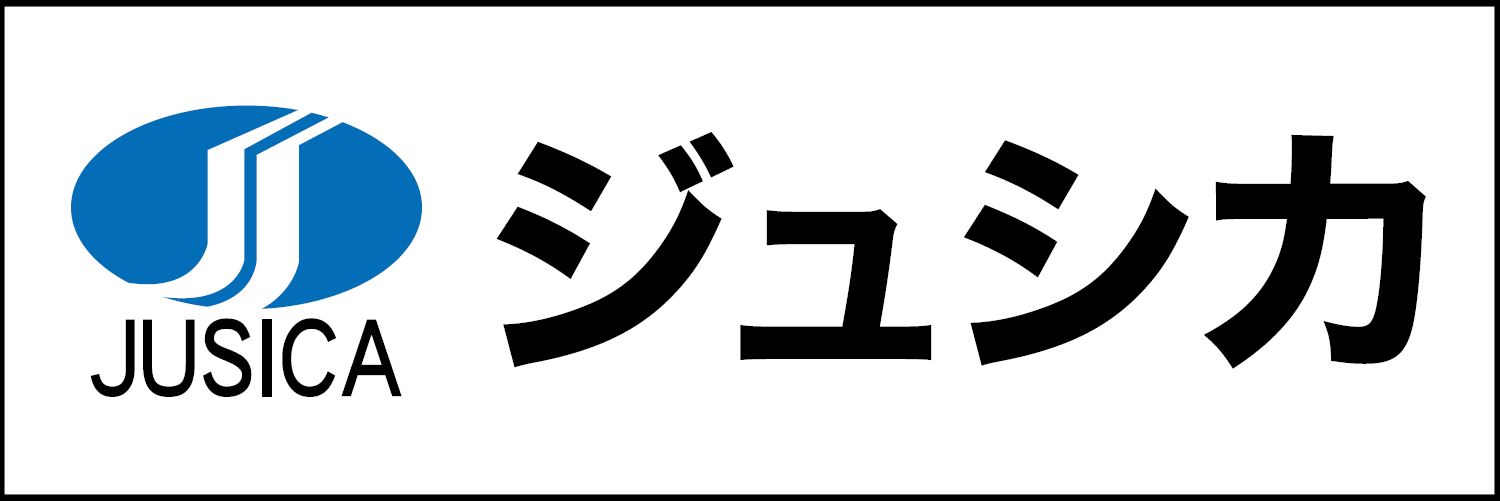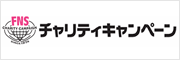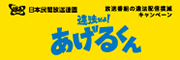知れば知るほど面白い!歴史ある坊津

週末、坊津の町歩きイベントに参加してきました。
日本三津(にほんさんしん)のひとつとして古い歴史がある坊津は、訪ねる毎に新たな発見があります。

イベントを主催したのはNPO法人「坊津やまびこ会」のみなさんです。
今回はかつて真言宗の寺院だった「一乗院」跡に残る仁王像が500才を迎えることを記念して、特別講師を招いての町歩きでした。

講師は鹿児島大学名誉教授の大木公彦先生と、テレビやラジオなどでおなじみ「まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会」代表の東川隆太郎さんのお二人。

一乗院跡には、かつての高僧が眠る四角墓(しかくばか)といわれる珍しい墓が並んでいます。使われている石は火山噴火によってできた溶結凝灰岩。鹿児島ならでは。
四角墓が数多く残っていることで、「一乗院がかなりの隆盛を誇っていたことがうかがえる」とのこと。一乗院の建立の歴史は古くはっきりしませんが6世紀ごろという説があります。

高さ2メートルを超える仁王像は、島津氏第14代当主島津勝久の頃に作られました。1522年の完成とされ今年で500才です。

講師のお二人による興味深い話を聞きながら、港近くの町中まで見学。
かつて交易の要所だった時代の名残があちこちに見られます。
江戸末期から明治初期のころに水を引くために作られた石管水道(せきかんすいどう)。当時は腕のある石工がいたはずです。

町歩きは午前中で終了。
地質や歴史にまつわるエピソードがまだまだあって時間が足りないほど。こうした薩摩の歴史を直接知る機会があるのはありがたいことです。

海が素晴らしい坊津にはダイビングで何度も訪れていましたが、「歴史と文化」という別の魅力があることを実感。「石の文化」という視点からの歴史講話も新鮮でした。
やまびこ会のみなさん、大木先生、東川さん、ありがとうございました。