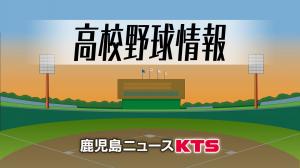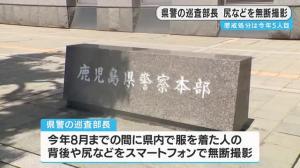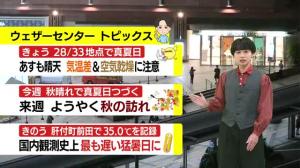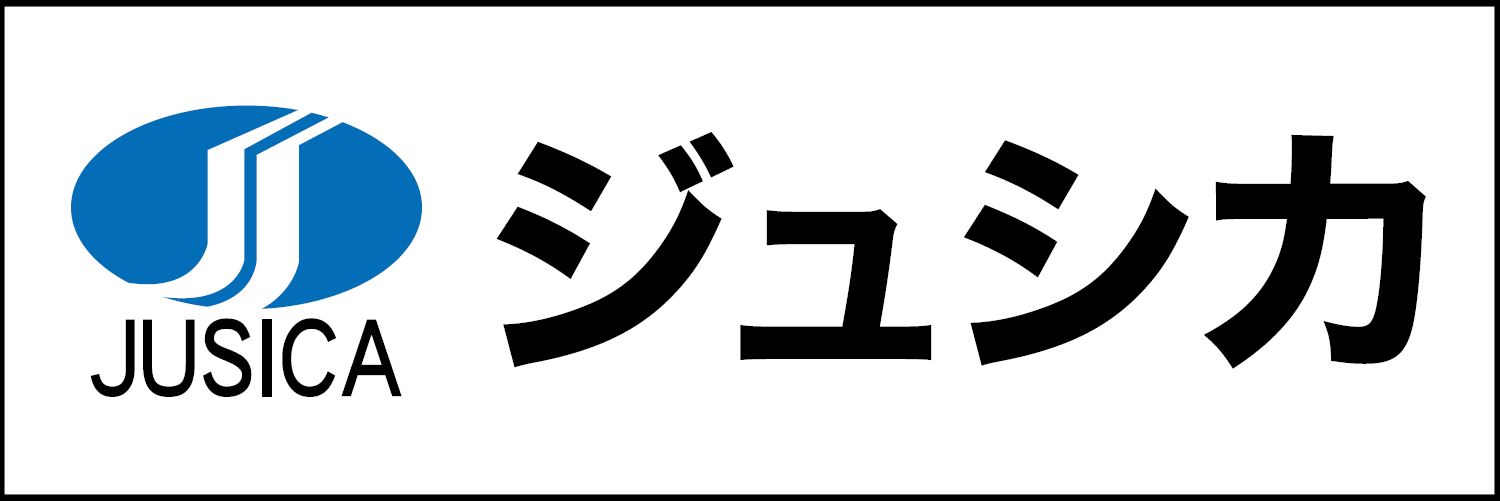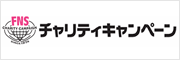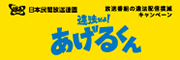スシロー未来型万博店でも提供! 「完全養殖カンパチ」の秘密に迫る ”未来の魚”で持続可能な漁業へ
2025年10月17日(金) 19:30
大阪・関西万博の「スシロー未来型万博店」で提供されていた、鹿児島県南大隅町の養殖カンパチを紹介します。
天然資源に頼らない「未来の魚」としても注目されているカンパチの秘密に迫ります。
日本一のカンパチの産地、鹿児島県。
その多くは、垂水市、鹿屋市、錦江町、南大隅町といった、錦江湾に面した大隅半島の自治体での養殖で生産されています。
うわさのカンパチが育てられているのは、こちらの南大隅町の沖合です。
小浜水産グループ・小浜洋志副社長
「南大隅、根占の漁場の特徴は潮流が速い。潮流が速いということはきれいな水が入れ替わることなので、水質が良く、魚の育ちが良い」
「未来の魚」を手がける小濱洋志さんです。
いけすを見せてもらいました。
エサを与えると元気に飛び跳ねるカンパチ。
小濱さん
「春に海づくり協会で生まれたものです」
実はこのカンパチ、垂水市で生産された稚魚から人の手で育てられた「完全養殖」のカンパチなんです。
鹿児島産のカンパチの約8割は、自然界で育った稚魚を養殖しています。
この稚魚を「天然種苗」と呼びますが、天然種苗は国内で十分な量を確保できず、多くを輸入に頼っているのが現状です。
一方で、限りある水産資源を守るため、「人工種苗」を使う「完全養殖」を広げることが「持続可能な漁業」のためには急務です。
時代に先駆けて10年前に完全養殖を始めた小濱さん。
当初は稚魚が全滅することもありましたが、消毒などの管理を徹底し、今では7割ほどを出荷できるまでになったそうです。
また、小濱さんのカンパチはエサやりに大きな特徴が!
きっかけとなったのは、「赤字」でした。
小濱さん
「コストが全然合わなくなって、生産コストを下げるしか方法がなくて、エサ代が経費の7割を占める業種なので」
小濱さんが試みたのは、エサやりの回数を半分にすること。
苦肉の策にも見えますが、これがカンパチの習性にピタリとハマりました。
小濱さん
「連続して給餌をすると吐き戻しもけっこう見えて、それを自分たちの目で確認しながら適切なタイミング、成長速度を追いながら時間をかけてやってきた」
回数を減らす分、エサの質にはとことんこだわり、「魚にとっていいもの」を与え続けたところ、エサ代は安くなったのに、おいしいカンパチができあがりました。
また、エサやりの回数を減らすことで、環境にもメリットが。
小濱さん
「残餌やふんが海底にたまって赤潮が発生したりするが、ここ最近、錦江湾は赤潮の被害もなく、環境も良くなってきている」
この取り組みに反応したのが大手回転寿司チェーンの「スシロー」です。
10月13日に幕を閉じた大阪・関西万博の「スシロー未来型万博店」で「あしたのサカナ」として提供されました。
その名も「秘蔵っこ鹿児島カンパチ」です。
スシローを運営するFOOD&LIFE COMPANIES・小澤魁人さん
「元々天然になかった魚を使っているので、これが持続性のある養殖の形になる。その形に注目して、カンパチには珍しいので『未来にも続いていく寿司』というメッセージを込めた。小濱さんのカンパチは非常に脂乗りが良くて味もある」
小濱さん自身も養殖の未来を見据えています。
小濱さん
「全部、私のグループを人工種苗、未来への魚に変えて、それを全世界に出荷するのが最終的な目標」
大隅から世界へ。
カンパチ養殖の現場では水産資源を守る地道な取り組みが続けられています。
小濱さんのカンパチは首都圏に出荷されていて、地元で食べられる場所はないのですが、2026年の春頃に小濱さんの育てたアカバナが、スシローで食べられるということです。
天然資源に頼らない「未来の魚」としても注目されているカンパチの秘密に迫ります。
日本一のカンパチの産地、鹿児島県。
その多くは、垂水市、鹿屋市、錦江町、南大隅町といった、錦江湾に面した大隅半島の自治体での養殖で生産されています。
うわさのカンパチが育てられているのは、こちらの南大隅町の沖合です。
小浜水産グループ・小浜洋志副社長
「南大隅、根占の漁場の特徴は潮流が速い。潮流が速いということはきれいな水が入れ替わることなので、水質が良く、魚の育ちが良い」
「未来の魚」を手がける小濱洋志さんです。
いけすを見せてもらいました。
エサを与えると元気に飛び跳ねるカンパチ。
小濱さん
「春に海づくり協会で生まれたものです」
実はこのカンパチ、垂水市で生産された稚魚から人の手で育てられた「完全養殖」のカンパチなんです。
鹿児島産のカンパチの約8割は、自然界で育った稚魚を養殖しています。
この稚魚を「天然種苗」と呼びますが、天然種苗は国内で十分な量を確保できず、多くを輸入に頼っているのが現状です。
一方で、限りある水産資源を守るため、「人工種苗」を使う「完全養殖」を広げることが「持続可能な漁業」のためには急務です。
時代に先駆けて10年前に完全養殖を始めた小濱さん。
当初は稚魚が全滅することもありましたが、消毒などの管理を徹底し、今では7割ほどを出荷できるまでになったそうです。
また、小濱さんのカンパチはエサやりに大きな特徴が!
きっかけとなったのは、「赤字」でした。
小濱さん
「コストが全然合わなくなって、生産コストを下げるしか方法がなくて、エサ代が経費の7割を占める業種なので」
小濱さんが試みたのは、エサやりの回数を半分にすること。
苦肉の策にも見えますが、これがカンパチの習性にピタリとハマりました。
小濱さん
「連続して給餌をすると吐き戻しもけっこう見えて、それを自分たちの目で確認しながら適切なタイミング、成長速度を追いながら時間をかけてやってきた」
回数を減らす分、エサの質にはとことんこだわり、「魚にとっていいもの」を与え続けたところ、エサ代は安くなったのに、おいしいカンパチができあがりました。
また、エサやりの回数を減らすことで、環境にもメリットが。
小濱さん
「残餌やふんが海底にたまって赤潮が発生したりするが、ここ最近、錦江湾は赤潮の被害もなく、環境も良くなってきている」
この取り組みに反応したのが大手回転寿司チェーンの「スシロー」です。
10月13日に幕を閉じた大阪・関西万博の「スシロー未来型万博店」で「あしたのサカナ」として提供されました。
その名も「秘蔵っこ鹿児島カンパチ」です。
スシローを運営するFOOD&LIFE COMPANIES・小澤魁人さん
「元々天然になかった魚を使っているので、これが持続性のある養殖の形になる。その形に注目して、カンパチには珍しいので『未来にも続いていく寿司』というメッセージを込めた。小濱さんのカンパチは非常に脂乗りが良くて味もある」
小濱さん自身も養殖の未来を見据えています。
小濱さん
「全部、私のグループを人工種苗、未来への魚に変えて、それを全世界に出荷するのが最終的な目標」
大隅から世界へ。
カンパチ養殖の現場では水産資源を守る地道な取り組みが続けられています。
小濱さんのカンパチは首都圏に出荷されていて、地元で食べられる場所はないのですが、2026年の春頃に小濱さんの育てたアカバナが、スシローで食べられるということです。