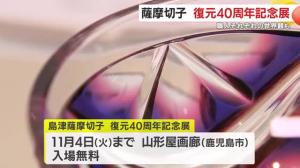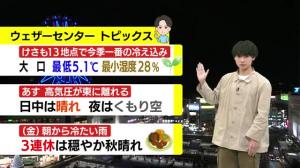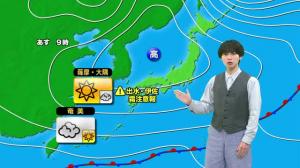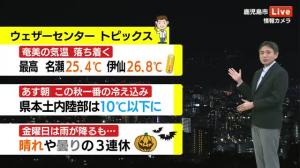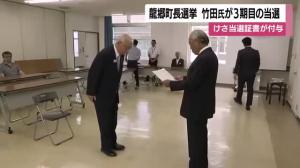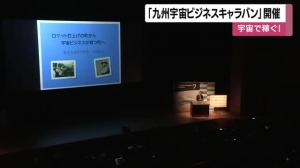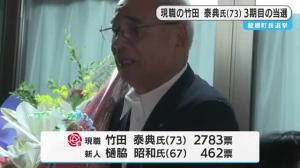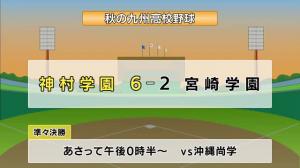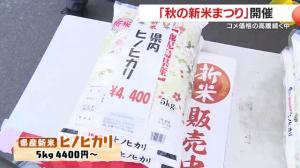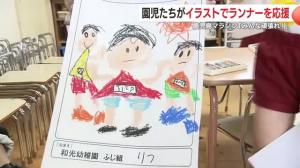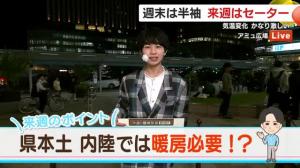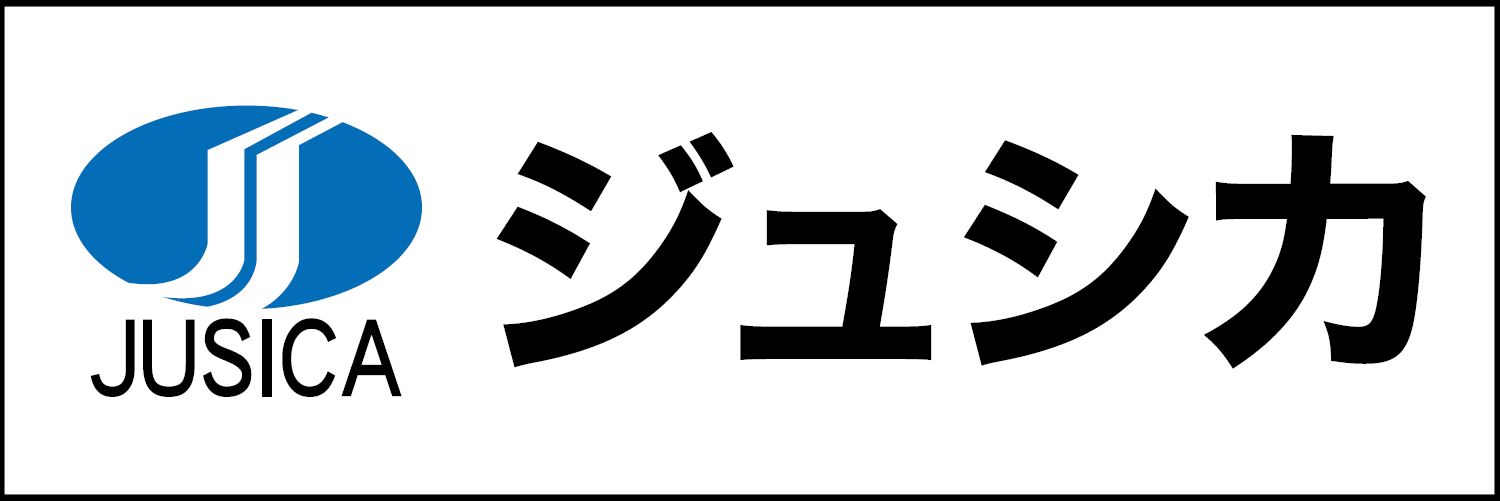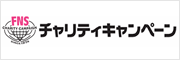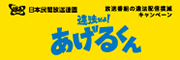3人に1人が高齢者の時代 老老介護の現場から 互助活動の取り組みなど鹿児島県内の現状を取材
2025年10月29日(水) 18:16
今、日本では国民の約3割が65歳以上の高齢者となり、高齢化社会まっただなかとなっています。
そんな中で顕在化している問題のひとつが高齢者が高齢者を介護する「老老介護」です。
老老介護の現場や互助活動の取り組みなど鹿児島県内の現状を取材しました。
鹿児島市に住む、こちらの夫妻。
80歳の夫が86歳の妻を介護する老老介護の家庭です。
2年前、妻は手のこわばりや姿勢を保つことが難しくなる難病と診断されました。
介護なしには生活を送ることが困難な要介護5に認定され、当初は介護施設に通院していましたが、本人の希望で2024年から在宅介護に切り替えました。
日中は夫が1人で妻の介護に当たります。これを機に料理も始めたそうです。
食べやすいように柔らかい食材を使ったり、一口大の大きさにした料理を、ゆっくり時間をかけて食べさせます。
Q.介護していて不安なこと
難病の妻を介護する夫(80)
「心の持ち方じゃないでしょうか。介護をさせられている、命令されてしているような気持ちに最初はずっとなっていた」
妻と訪問看護師の会話
「朝の薬は9時前に飲んだの」
「(次の薬まで)間が空いているからいいですね」
お昼すぎから夕方までは、訪問看護を活用して入浴やリハビリの支援を受けています。
夫はこうした時間を、食材の買い出しや、友人らとの会話などにあてていると言います。
難病の妻を介護する夫(80)
「オンオフが少しはできた方がいいかも。そうしないと自分がこう(縛り付けられているように)なってしまう」
「(介護は)終わりが分かってないからな。ここまですれば終わりということもなくて。スタートしたらずっと走り続けないといけない」
「素直に見られるようになったらいいな。顔を向けられたら一番いいんじゃないかな。最近愛おしくなりましたね」
国の高齢化率は比較可能な2020年のデータで28.8%。
鹿児島県内は32.5%と全国平均を上回り、南大隅町や錦江町では40%を超えています。
高齢化率が上がる中、必然的に増えるのが介護をする側、される側の双方が高齢者となる「老老介護」です。
体力の低下などで介護する側に大きな負担がかかる中、懸念される「共倒れ」。それが最悪の形であらわれてしまったのが、2024年8月、鹿児島県阿久根市で起きた事件です。
77歳夫が認知症の75歳の妻を介護疲れで殺害。
実刑判決を受けた夫は裁判で自分も死ぬつもりだったことを明かしました。
どうすれば、このような悲劇を防ぐことができるのか…
高齢者と地域のかかわりなどに詳しい鹿児島大学の池田由里子助教は、次のように話します。
鹿児島大学 医学部・池田由里子助教
「更なる負担につながらないように手を差し伸べる、もしくは差し伸べたいと思うようなコミュニティー作りが大事と思う」
当事者だけでは乗り越えることが難しい老老介護。
そんな中、鹿児島県が2014年から始めたのが「高齢者地域支え合いグループポイント事業」です。
65歳以上の高齢者3人以上のグループでボランティアなどを行うとポイントがたまり、地域商品券などに交換できます。
地域の高齢者同士のつながりを生み出すことで老老介護の家庭の支援にもつなげることが狙いの一つで、2024年は約3万7000人が活動に参加しました。
高齢化率が41.4%の肝付町。
「おはようございます」
民家に集まったのはこの事業に参加する「いったんもめんと結いの会」のメンバーです。
2016年に波野地区と有明地区の住民で結成され、現在は71歳から86歳の12人が、毎週水曜日におかずのおすそ分け活動に取り組んでいます。
Q.きょうのメニューは?
A.筑前煮と酢の物とマカロニのケチャツプと酢ゴボウ
おかずは事前予約制。この日は約100人分の食材が台所に並びました。
おかずを頼む人の多くが高齢者で食べやすいよう食材を細かく切るのがポイントの1つです。
そうして出来上がったのがこちらのおかず。
「いってきます」
おかずは、地域住民の見守りも兼ねて、直接、住民のもとへ届けます。
かつて配達中に、熱中症で倒れている人を見つけたこともあるそうです。
購入した人
「自分で作らないものを色々作って下さるからうれしいです」
活動を始めて9年、メンバーもやりがいを感じているようです。
いったんもめんと結いの会・城之尾 八重子さん
「(活動でポイントが貰えることは)皆さん張り合いになりますよね。何もなくただボランティアでやっているだけではやっぱり皆さん物足りない」
いったんもめんと結いの会・豊重 サミエさん
「みんなそれぞれに薬をのみながらだけど、みんなが薬を全くのまないということは少ないから、私だけでじゃないんだと思ってそこでも元気をもらえる」
このような活動を通して交流を重ねることは、老老介護の当事者に手を差し伸べるひとつのきっかけになりそうです。
ただしその一方で、池田助教はそれだけでは救いきれない人たちの存在を指摘します。
鹿児島大学 医学部・池田由里子助教
「新しいコミュニティーに属することが苦手な方もいる現実があるので、そのような方々をどうやってこちらが支援の手を差し伸べるかということが非常に課題と考えている」
老老介護の家庭にどうアプローチし、どんなサービスを提供するのか。
高齢化社会が進む中、国全体で考えなくてはいけない大きな課題と言えそうです。
そんな中で顕在化している問題のひとつが高齢者が高齢者を介護する「老老介護」です。
老老介護の現場や互助活動の取り組みなど鹿児島県内の現状を取材しました。
鹿児島市に住む、こちらの夫妻。
80歳の夫が86歳の妻を介護する老老介護の家庭です。
2年前、妻は手のこわばりや姿勢を保つことが難しくなる難病と診断されました。
介護なしには生活を送ることが困難な要介護5に認定され、当初は介護施設に通院していましたが、本人の希望で2024年から在宅介護に切り替えました。
日中は夫が1人で妻の介護に当たります。これを機に料理も始めたそうです。
食べやすいように柔らかい食材を使ったり、一口大の大きさにした料理を、ゆっくり時間をかけて食べさせます。
Q.介護していて不安なこと
難病の妻を介護する夫(80)
「心の持ち方じゃないでしょうか。介護をさせられている、命令されてしているような気持ちに最初はずっとなっていた」
妻と訪問看護師の会話
「朝の薬は9時前に飲んだの」
「(次の薬まで)間が空いているからいいですね」
お昼すぎから夕方までは、訪問看護を活用して入浴やリハビリの支援を受けています。
夫はこうした時間を、食材の買い出しや、友人らとの会話などにあてていると言います。
難病の妻を介護する夫(80)
「オンオフが少しはできた方がいいかも。そうしないと自分がこう(縛り付けられているように)なってしまう」
「(介護は)終わりが分かってないからな。ここまですれば終わりということもなくて。スタートしたらずっと走り続けないといけない」
「素直に見られるようになったらいいな。顔を向けられたら一番いいんじゃないかな。最近愛おしくなりましたね」
国の高齢化率は比較可能な2020年のデータで28.8%。
鹿児島県内は32.5%と全国平均を上回り、南大隅町や錦江町では40%を超えています。
高齢化率が上がる中、必然的に増えるのが介護をする側、される側の双方が高齢者となる「老老介護」です。
体力の低下などで介護する側に大きな負担がかかる中、懸念される「共倒れ」。それが最悪の形であらわれてしまったのが、2024年8月、鹿児島県阿久根市で起きた事件です。
77歳夫が認知症の75歳の妻を介護疲れで殺害。
実刑判決を受けた夫は裁判で自分も死ぬつもりだったことを明かしました。
どうすれば、このような悲劇を防ぐことができるのか…
高齢者と地域のかかわりなどに詳しい鹿児島大学の池田由里子助教は、次のように話します。
鹿児島大学 医学部・池田由里子助教
「更なる負担につながらないように手を差し伸べる、もしくは差し伸べたいと思うようなコミュニティー作りが大事と思う」
当事者だけでは乗り越えることが難しい老老介護。
そんな中、鹿児島県が2014年から始めたのが「高齢者地域支え合いグループポイント事業」です。
65歳以上の高齢者3人以上のグループでボランティアなどを行うとポイントがたまり、地域商品券などに交換できます。
地域の高齢者同士のつながりを生み出すことで老老介護の家庭の支援にもつなげることが狙いの一つで、2024年は約3万7000人が活動に参加しました。
高齢化率が41.4%の肝付町。
「おはようございます」
民家に集まったのはこの事業に参加する「いったんもめんと結いの会」のメンバーです。
2016年に波野地区と有明地区の住民で結成され、現在は71歳から86歳の12人が、毎週水曜日におかずのおすそ分け活動に取り組んでいます。
Q.きょうのメニューは?
A.筑前煮と酢の物とマカロニのケチャツプと酢ゴボウ
おかずは事前予約制。この日は約100人分の食材が台所に並びました。
おかずを頼む人の多くが高齢者で食べやすいよう食材を細かく切るのがポイントの1つです。
そうして出来上がったのがこちらのおかず。
「いってきます」
おかずは、地域住民の見守りも兼ねて、直接、住民のもとへ届けます。
かつて配達中に、熱中症で倒れている人を見つけたこともあるそうです。
購入した人
「自分で作らないものを色々作って下さるからうれしいです」
活動を始めて9年、メンバーもやりがいを感じているようです。
いったんもめんと結いの会・城之尾 八重子さん
「(活動でポイントが貰えることは)皆さん張り合いになりますよね。何もなくただボランティアでやっているだけではやっぱり皆さん物足りない」
いったんもめんと結いの会・豊重 サミエさん
「みんなそれぞれに薬をのみながらだけど、みんなが薬を全くのまないということは少ないから、私だけでじゃないんだと思ってそこでも元気をもらえる」
このような活動を通して交流を重ねることは、老老介護の当事者に手を差し伸べるひとつのきっかけになりそうです。
ただしその一方で、池田助教はそれだけでは救いきれない人たちの存在を指摘します。
鹿児島大学 医学部・池田由里子助教
「新しいコミュニティーに属することが苦手な方もいる現実があるので、そのような方々をどうやってこちらが支援の手を差し伸べるかということが非常に課題と考えている」
老老介護の家庭にどうアプローチし、どんなサービスを提供するのか。
高齢化社会が進む中、国全体で考えなくてはいけない大きな課題と言えそうです。